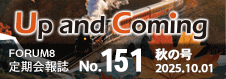| �p�Q�|�P�D |
�n�Ճf�[�^�Ő��ʗL������͂��܂����A��̑w�Ő��ʗL��Ƃ����ۂɉ����w�܂ł��̐��ʂ͂���Ƃ����̂��A�܂�A���ʗL��̃X�C�b�`�́A��ԏ�̐��ʑw�̂ݐݒ肷��悢�̂��H |
| �`�Q�|�P�D |
�������A�Ⴂ�܂��B�n�Ճf�[�^�̐��ʊ֘A�̃f�[�^�i���ʗL���A���ʁj�́A���̒n�w�ɑ��Ă̂ݗL���Ƃ��Ĉ����܂��B�t�Ɍ����A�n�w���ɐ��ʃf�[�^��������ƒ�`����K�v������܂��B�T�w�n�ՂłR�w�ڂ������s�����w�ł���ꍇ�́A�P�A�Q�A�S�A�T�w�ɑ��Đ��ʊ֘A�̃f�[�^����͂��Ă��������B |
| �@ |
|
| �p�Q�|�Q�D |
�@��i�K���̐��ʓ��͂�����܂��A�ǂ̂悤�ɑΏ�����悢�̂ł��傤���H |
| �`�Q�|�Q�D |
�w�ʑ��̐��ʂ��@��i�K���ɕω�����Ƃ������Ƃ͖w�ǂȂ��Ǝv���܂��̂ŁA�@�푤�ɂ��Ă͐������܂��B�{�v���O�����ł́A�����I�Ɋe�@��i�K�ɂ�����@��ʂ���ɂ͐��ʂ��Ȃ����̂Ƃ��đ������v�Z���܂��B���Ȃ킿�A�n�Ճf�[�^�œ��͂���̂́A�����܂ł��@��O�̏�Ԃ���͂��A�y���A�������͌@��ʂ��牺�̒n�Ճf�[�^��ΏۂɁA�@��ʂ���ɒ�`���ꂽ���ʂ͌@��ʂ܂ŋ����I�ɉ����Čv�Z�����܂��B�������A���ݎw�j�o�S�R�ɐ}�����Ă���悤�ɁA�Ǒ̐�[���܂܂��n�Ղ����w�̏ꍇ�́A���̐�[�n�w�Ɍ��萅�����v�Z���鐅�ʂ́A���͂��ꂽ�@��O�̐��ʁi�@��ʂ���Ȃ�Ώ�̂܂܂Łj�����̂܂g
�p���܂��B
����āA�@��i�K���ɐ��ʂ��܂ޒn�Ճf�[�^�̓��͕͂K�v����܂���B����̔w�i�ɁA�@�푤�ɐ��ʂ��c��A�����鐅���@��̏�Ԃ��\���ۂ��Ƃ������Ƃ�����̂ł���A�c�O�Ȃ���A����̓T�|�[�g�O�ł��B |
| �@ |
|
| �p�Q�|�R�D |
�n�Չ��ǂ��l���ł��܂���H�n�Ճf�[�^�ōŏ�����y����ύX���ē��͂���̂ł����H |
| �`�Q�|�R�D |
[��{�f�[�^]�_�C�A���O�|[�v����]��ʂ��m�F���Ă��������B�����ɁA�n�Չ��ǂ̗L���Ƃ����X�C�b�`������܂��B�����[������]�ɂ��Ă��������B����ɂ���āA[�n�Ճf�[�^]�_�C�A���O��[�n�Չ��ǃf�[�^]�^�u���p�ӂ���܂��B������Œn�Չ��ǃf�[�^����͂��Ă��������B�����āA�n�Ճf�[�^�ɉ��nj�̃f�[�^����͂���Ƃ������Ƃł͂���܂���B |
| �@ |
|
| �p�Q�|�S�D |
�`��o�l�W���Ƃ͉��ł����H |
| �`�Q�|�S�D |
�g���l���W���������ł́A�o�P�T�X�`�o�P�U�P�ɐ������Ȃ���Ă��܂��B�����ł́A���R�y���߂̌`��ɂ���ẮA�y���߉ˍ\�̎O�����I�Ȍ��ʁi�`����ʁj��v�ɍl�����邱�Ƃ��ł���Ƃ���A�@��`���R�̏ꍇ�A�~�`���R�̏ꍇ�̐���������܂��B��`�̏ꍇ�͌`��o�l�A�~�`�̏ꍇ�̓����O�o�l�ƌĂ�ł���悤�ł��B�l�̎Z�o���@�͕����ɂ����̂Ƃ��āA�{�v���O�����ł́A���̌`��o�l�����͂����ƁA�e���o�l�Ƃ��ĕǑ̂ɏ펞���̌`��o�l���������̂Ƃ��ĉ�͂��s���܂��B�l�����Ȃ��ꍇ�̓[������͂��Ă��������B |
| �@ |
|
| �p�Q�|�T�D |
���̖{���������i�łQ�{�܂łƂ��Ă��܂����A����ȏ�͑Ή����Ȃ��̂��H |
| �`�Q�|�T�D |
�����i�ɂR�{�ȏ�肪�ݒu����邱�Ƃ͂Ȃ��낤�Ɣ��f���܂����B�R�{�ȏ゠��ꍇ�Ȃǂ́A���萔�ł����A�g�p�{�����̎x�ۍH�g�|�̍�����[��l]�|[�x�ۍH�p�g�|�e�[�u��]�ɂĂ����g�Œlj��o�^����A[�x�ۍH�f�[�^]�ł��̒lj��o�^�g�|�m������͂��A�{���͂P�{�ɂ���ȂǂőΏ����Ă��������B�Б����f���Ŏx�ۍH�o�l�̒l�����O�ɂ킩���Ă���ꍇ��[��{�f�[�^]�_�C�A���O��[�v�Z���@]�ɂ���x�ۍH�o�l�̈������u�o�l�l���ړ��́v�ɂ��Ē����Ă����\�ł��B |
| �@ |
|
| �p�Q�|�U�D |
��̎��̐��ւ���̃o�l�������v�Z�ɂȂ�܂��H |
| �`�Q�|�U�D |
���ւ��H�i��j�ɂ��ẮA���ۂɎx�ۍH�`���Őݒu����ꍇ�▄�ߖ߂��y�̔C�ӂ̈ʒu���x�_�o�l�Ƃ��ĕ]������ꍇ�A����ɂ͎̂ăR�����x�_�Ƃ���ꍇ�Ȃǂ����낤���ƍl�����܂��B
�x�ۍH�`���̏ꍇ�͂��w�E�̒ʂ�A�g�p�|�ށA�����A�ݒu�Ԋu��������o�l�l���v�Z���邱�Ƃ͊ȒP�ł����A��Ɏ������悤�Ȃ��낢��ȃp�^�[���ɁA�킩��₷�����͏�����Ή�����̂����X����ł���Ɣ��f���A���ڃo�l�l����͂���Ƃ����V���v���ȕ��@���̗p���܂����B���ւ��H���̂��̂̎{�H�@�Ȃǂ��Ȃ�ɐ�����������ŁA�Ή��������������Ǝv���܂��B |
| �@ |
|
| �p�Q�|�V�D |
�A���J�[�����y���߂���������ہA�ǂ̂悤�ɂ��Ďx�ۍH�o�l���Z�o����悢���H
|
| �`�Q�|�V�D |
���݂̐��i�ł́A���ڃO�����h�A���J�[�����̐v���s�����Ƃ��o���܂��A�x�ۍH�o�l�ɒ��ځA�O�����h�A���J�[�ɑ������鐅�������o�l�l����͂���A�P�ʕ��i�P��������j�̃A���J�[���͒l�i�������A�������́j�鎖���ł���ƍl�����܂��B�ȉ��̎菇�Ō������������B
�菇�P
�u��{�f�[�^�v�́u�v�Z���@�v�́u�x�ۍH�o�l�̈����v���u�o�l�l���ړ��́v�Ƃ���B
�i���̏ꍇ�A���[�������f���͂ł��܂���j�B
�菇�Q
�u�x�ۍH�f�[�^�v�Łu�x�ۍH�o�l�l�v����͂���B
�A���J�[�����o�l�l�ɂ��ẮA���ݎw�j�o�D�P�O�W�ɉ�����������Ă��܂��B
�j���d�~�`�~�������O�Q�i���j�^�i�k�~���j
�����ɁA
�@�j�F���������o�l�l�i���m�^���O�Q�j
�@�d�F�����ނ̃����O�W���i���m�^���O�Q�j
�@�`�F�����ނ̒f�ʐρi���O�Q�j
�@�k�F�����ނ̎��R���i���j
�@���F�A���J�[�̐����Ԋu�i���j
�@���F��������̃A���J�[�X�p�i�x�j
�ȏ�ŁA�e�Y����͂��s�����Ƃɂ��A���ɖ��Ȃ��A�������͂܂ł͓�������̂ƍl�����܂��B
�i���j
����ꂽ���͂���O�����h�A���J�[�w�j�Ȃǂɏ]���A�ʓr�A���J�[�ƍ����K�v������܂��B
�{�v���O�����ł͔��͒l�݂̂̎Z�o�ƂȂ�܂��̂ŁA�����Ӊ������B |