
|
|
|
土留め工の設計 Ver.6について紹介させて頂きます。本バージョンでは、(1)土地改良事業標準設計への対応、(2)ハット形鋼矢板・軽量鋼矢板の対応、(3)コンクリート矢板の対応、(4)SMWの等厚壁(TRD工法)への対応、(5)腹起しの2重(横並び)設置の対応、(6)その他の要望対応などを行いました。
■土地改良事業標準設計への対応
『土地改良事業計画設計基準 設計「水路工」 基準書 技術書』(平成13年2月
農水省)に準拠した自立式矢板型水路の設計に対応しました。制限事項として、(1)支保工の形式は自立式のみ、(2)壁体の種類は鋼矢板および軽量鋼矢板(腐食を考慮)、コンクリート矢板、(3)設計方法は慣用法のみとなります。矢板に作用する荷重として、自動車荷重および盛土荷重を考慮することが可能です。
自立式矢板の設計方法は、基本的にChangの式になります。しかしながら、仮設構造物の設計では掘削底面を設計面とするのに対して、本基準では、図1に示すように、主働土圧強度と残留水圧強度の和が受働土圧強度と等しくなる位置を仮想地盤面(設計面)として扱う点が大きく異なります。 |
|
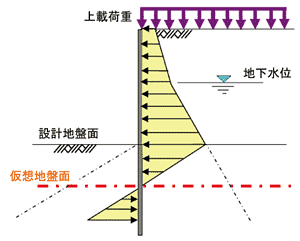
▲図1 仮想地盤面 |
■ハット形鋼矢板・軽量鋼矢板の対応
土留め壁に用いる鋼材として、新たにハット形鋼矢板および軽量鋼矢板を追加しました。これにより鋼矢板としましては、(1)従来のU形鋼矢板、(2)ハット形鋼矢板、(3)型式A〜Cの軽量鋼矢板、(4)型式DおよびE(ハット形)の軽量鋼矢板の4種類が適用可能となりました。本製品では、初期入力にて採用する鋼矢板のタイプを指定することにより、選択された基準を考慮した継手効率(表1)を自動セットいたします。
▼表1 鋼矢板、軽量鋼矢板の継手効率
| |
鋼矢板 |
軽量鋼矢板 |
| 普通 |
ハット形 |
普通(型式A〜C) |
ハット形
(型式D,E) |
| 土地改良基準 |
他の基準 |
土地改良基準 |
他の基準 |
根入れ計算に用いるβ算出用
(慣用法) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
断面力、変位計算に用いるβ算出用
(慣用法) |
0.80 |
0.45 |
1.00 |
0.80 |
0.60 |
1.00 |
断面二次モーメント用
(変位、断面力) |
0.80 |
0.45 |
1.00 |
0.80 |
0.60 |
1.00 |
| 断面係数用(応力度) |
1.00 |
0.60 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
■コンクリート矢板の対応
前述の鋼矢板に加え、土留め壁の種類として更にコンクリート矢板(RC部材)を追加しました。コンクリート矢板の断面形状として、(1)平形、(2)溝形、(3)波形の3種類を選択することが可能です。コンクリート矢板は主に永久構造物に利用することの多い部材ですが、本製品を使用することにより仮設時の検討を行うことが可能となります。コンクリート矢板の平形および溝形は、配筋状態の関係上、支保工形式によって施工する向きが決められておりますが、本製品ではその向きを設計者が設定できるように配慮しております。また、コンクリート矢板は規格により製品長さが決められていますので、本製品では計算実行時に決定された壁長がその製品長さの範囲を超えている場合には警告を表示するように配慮しています。 |
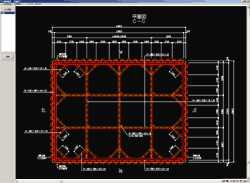
▲図2 図面生成画面(コンクリート矢板−波形) |
■SMWの等厚壁(TRD工法)の対応
本製品は、これまでSMW壁として柱列式タイプをサポートしておりましたが、本バージョンより等厚式も適用できるようになりました。等厚壁を採用した場合の設計は、『TRD工法
技術資料』(平成20年7月 TRD工法協会)に準じて行います。芯材の断面照査につきましては柱列式と同様ですが、ソイルセメント(中間ソイル)の断面照査がTRD工法独自の方法となります。また、本製品では、芯材の仕様による必要壁厚の照査を検討することが可能となっています。また、等厚壁は任意な間隔で芯材を設置できることが特徴のひとつですが、本製品では、設計計算は、一番危険と考えられる最大間隔で照査していただき、作図時は任意の間隔で図面を生成することが可能です。
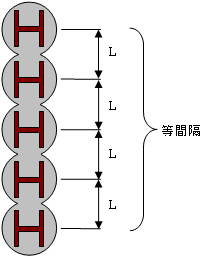
柱列壁 |
|
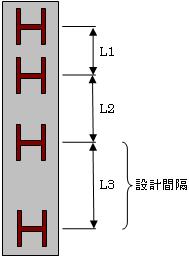
等厚壁(TRD工法) |
▲図3 柱列壁、並びに、等厚壁の芯材間隔 |
■腹起しの2重(横並び)設置の対応
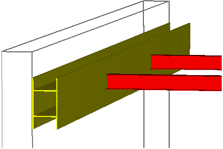
多段腹起し |
|
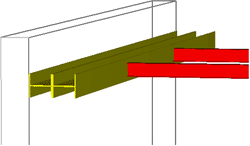
2重腹起し |
| ▲図4 多段、並びに、2重腹起し |
本製品は、Ver.2において腹起しの多段(縦並び)設置に対応しておりますが、この度ご要望の多かった2重(横並び)設置に対応しました。これにより、各支保工の設置位置ごとに多段または2重の指定が可能となります。なお、製品の制限事項といたしまして2重腹起しの場合には多段とすることはできません。
図5は、2重腹起しのメインウィンドウ4面図です。長手方向の腹起しを2重にすることで、切梁を設けずに土留め壁の構築が可能になるかの検討などが行えます。
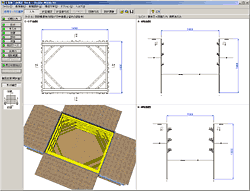
▲図2 図面生成画面(コンクリート矢板−波形) |
|
今回新しく対応した「ハット形鋼矢板」、「コンクリート矢板」、「等厚壁(TRD工法)」について説明させて頂きます。
■ハット形鋼矢板
鋼矢板は400mm幅のU形鋼矢板が仮設工事などではよく用いられていますが、建設コストを縮減するために広幅型鋼矢板が平成9年に登場すると、本設ではこれが主流となっています。さらに、平成16年には、施工性、構造信頼性、経済性に優れた新世代鋼矢板として、ハット(帽子)形状をした有効幅900mmの鋼矢板が開発されました。
ハット形は、壁体構築後の中立軸と鋼矢板1枚あたりの中立軸が一致する断面形状であるために、従来のU形鋼矢板と異なり、継手効率による断面性能の低減を考慮する必要がないことが設計上の大きな利点と考えられます。現在は本設工事に使用されていますが、今後、仮設工事にも用いられることも十分考えられることから、本プログラムにて対応することにしました。 |
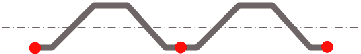 |
| ハット形(新世代鋼矢板) |
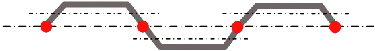 |
U形鋼矢板
▲図6 ハット形と従来形の継ぎ手状態の違い |
参考文献:
(1)新しい熱間圧延鋼矢板「ハット形鋼矢板900」 JFE技報No.10 製品・技術紹介 2005年12月
(2)鋼管杭協会:ハット形鋼矢板900-単一圧延材として世界最大幅の鋼矢板、基礎工、Vol.34、No.1、2006年
■コンクリート矢板
コンクリート矢板の特長として以下が挙げられます。
| (1) |
工場生産による高強度コンクリート断面で徹底した重量軽減化が図られ、運搬・施工が容易で経済性に優れている。 |
| (2) |
安定した品質により、永久構造物としての美観と耐久性を保持している。 |
用途としては、河川護岸、都市水路、暗渠、道路土留めなどがあり、いずれも永久構造物ですが、仮設状態の検討も必要となりますので、本製品でサポートすることに致しました。将来的には、本設設計にも対応したいと考えております。コンクリート矢板では、図7に示す「平形」「溝形」では、配筋状態により、引張側と圧縮側があり、それぞれひび割れモーメントの値が異なりますので、断面の配置方向に注意して断面照査を行う必要があります。 |
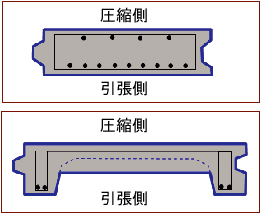
▲図7 平形、溝形の配筋状態 |
■等厚壁ソイルセメント地中連続壁(TRD工法)
TRD工法は、カッターチェーンを用いて等厚のソイルセメント地中壁を連続的に施工する技術です。一般土砂地盤では最深で約57mの大深度土留め壁の施工実績があるようです。本工法は次のような特徴があります。
(1)抜群の安定性 : 低重心設計により、柱列式工法(オーガー攪拌方式)と比較して機械高が大幅に低く、安全施工が可能である。
(2)高精度施工が可能 : 直進性、鉛直性に優れた高精度施工が可能である。
(3)優れた掘削能力による省コスト実現 : 硬質地盤に対しても掘削能力が高く、工期短縮、コストの縮減が可能である。
(4)深度方向に均質な壁品質 : 深度方向に強度のばらつきが極めて少ない均質な壁が造成できる。
(5)芯材間隔の任意設定が可能 : 壁形状が等厚であり、任意の間隔で芯材建込みができる。
本工法に対応するにあたり、当初は「TRD工法技術資料」(平成17年、TRD工法協会)に基づいて開発を行っておりましたが、TRD協会様のご協力により、平成20年7月発行の最新のTRD工法技術資料に対応することができました。新技術資料では、中間ソイルの応力検討を直線山形アーチ法から図8に示す放物線アーチ法に変更となっております。
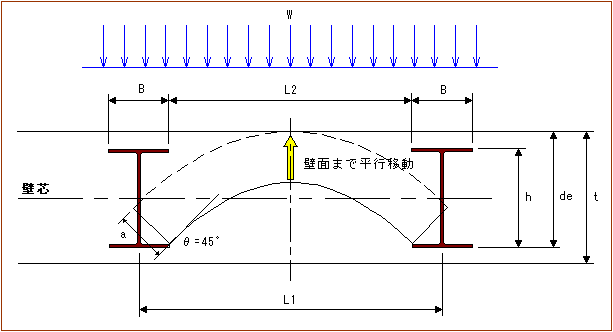
▲図8 平形、溝形の配筋状態 |
以上、本製品で対応可能な壁体種類を図9に整理しました。
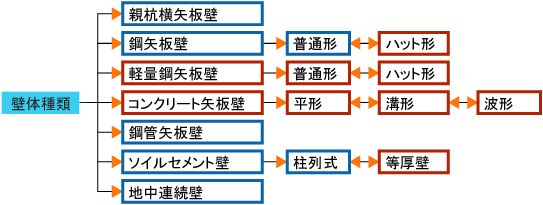
▲図9 壁体種類一覧 |
今回の改訂(赤囲み箇所)により、壁体種類が全7種類に拡張され、鋼矢板、軽量鋼矢板壁は2タイプ、コンクリート矢板は3タイプ、ソイルセメント壁は2タイプの選択が可能になりました。豊富な断面種類並びに断面タイプに対応したことで、より一層、検討範囲が拡張されたものと考えております。
本製品の開発にあたり、ジオスター株式会社様、TRD工法協会様のご協力、並びに、ご助言を頂戴しましたことに心より感謝致します。今後も機能改善、機能追加を行い、よりよい製品開発に努力してまいりたいと考えております。
土留め工の設計セミナー  詳細 詳細
●日時 10月 22日(水) 13:30 〜 16:30 ●参加費 無料
●本会場 フォーラムエイト東京本社 GTタワーセミナールーム TV会議システムにて 東京・大阪・名古屋・福岡にて同時開催
本セミナーは、(社)地盤工学会CPDプログラム(5.5ポイント)に認定されています。 |
●第2回FORUM8デザインコンファランス 技術セッション : 設計CAD  詳細 詳細
●日時 9月19日(金) 9:30 〜 16:30 ●参加費 無料
●本会場 フォーラムエイト東京本社 GTタワーセミナールーム
TV会議システムにて 東京・大阪・名古屋・福岡・上海・北京・ソウルにて同時開催(一部講演に限る)
●特別講演 : 「土留め工の設計とFEM解析の利活用」 群馬大学 工学部助教 蔡 飛 氏
●開発者講演 : 「土留め工の設計・新バージョン解説」 |
■土留め工の設計 Ver.6 リリース予定日:2008年8月末
|
(Up&Coming '08 秋の号掲載) |
 |
|







>> 製品総合カタログ

>> プレミアム会員サービス
>> ファイナンシャルサポート
|








