| New Products |
|
|
土留め工の設計Ver.9 |
| 土留め工の設計セミナー |
CPD |
●日 時 : 2011年9月6日(火)9:30〜16:30
●参加費 : 1名様 \15,000(税込\15,750)
●本会場 : FORUM8東京本社GTタワーセミナールーム
※TV会議システムにて、5会場同時開催 |
|
|
慣用設計法及び弾塑性法による土留め工解析・図面作成プログラム |
|
|
|
土留め工の設計Ver.9のリリースにあたり、新機能を中心にご紹介いたします。新バージョンでは、
- 外的安定性の検討
- 30度60度隅火打ちに対応
- 全登録鋼材の断面応力度照査に対応
- アンカー式土留めで軸力分担幅と腹起し設計スパンが異なる場合の計算に対応
- 控え杭タイロッド式土留めでタイロッド間隔と控え杭間隔が異なるケースへの対応
- その他要望対応
などを行いました。
|
外的安定性とは、土留め壁が斜面上に設置される場合(図1)、また構造物とアンカーとの力のやりとりには関係なく構造物とアンカー体を含んだ土塊全体がすべる場合(図2)等、土留めを含む地盤全体の安定性です。
外的安定性が不足する場合には、基本的な計画の見直し、あるいはこの安定を満足するための対策工について検討しなければなりません。
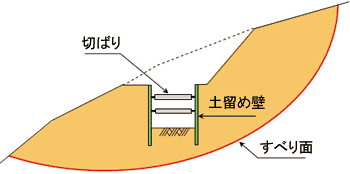 |
|
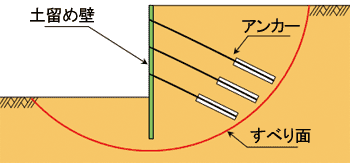 |
■図1 外的安定性
(土留め壁が斜面上に設置される場合) |
|
■図2 外的安定性
(構造物とアンカー体を含んだ土塊全体がすべる場合) |
本プログラムでは、すべり円中心が格子範囲内にある不特定多数のすべりに対する臨界面(最小安全率)の計算を縦横メッシュの格子上で行ない、その中で最小安全率となるすべり円を抽出する処理を行います(図3)。
外的安定の計算データは当社「斜面の安定計算」用のデータとして保存することができますので、「斜面の安定計算」を活用することによって、より詳細な検討や対策工の検討等を行うこともできます。
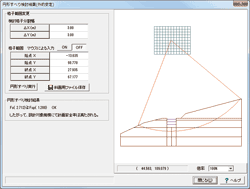 |
| ■図3 円弧すべり検討結果画面 |
|
隅火打ちは45度で設置されるのが一般的ですが、現場の状況等によっては30度60度で設置することがあるようです。本プログラムでは、そのような状況にも対応できるように今回隅火打ちの角度を「30度」「45度」「60度」から選択できるようにしました。当然ながら、切ばり支保工設計時の内部算定スパンも入力された角度に応じて計算を行います(図4)。
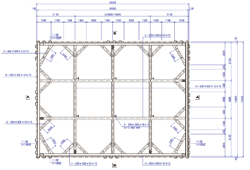 |
| ■図4 30度60度隅火打ちの図面例 |
|
壁体断面照査の結果総括表画面にて、登録されている全鋼材についての応力度照査結果を参考値として確認できる機能を追加しました。設定した鋼材で結果がNGになった場合には、こちらの機能を利用することにより選択し直す鋼材の目安がつきやすくなると考えられます(図5)。
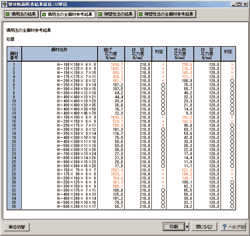 |
| ■図5 全鋼材参考結果画面 |
|
| アンカー式土留めで軸力分担幅と腹起し設計スパンが異なる場合の計算に対応 |
アンカー支保工の場合に、Ver.8まではアンカーの設計間隔(軸力分担幅)と腹起しの設計間隔は同じ間隔であるものとして、図6のL1、L2などを用いていましたが、本バージョンよりアンカーの設計間隔を下式で計算した値に変更し、かつ、腹起しの設計間隔につきましては、設計アンカーとは別に任意のスパンを選択できるようにしました。
・指定したアンカーが端部の場合(図6のアンカー1、アンカー3)
端部側はスパン全長、中央側はスパンの半分とします。
アンカー設計間隔
Sa1=L1+L2/2、
Sa3=L3/2+L4
・指定したアンカーが中央の場合(図6のアンカー2)
両側スパンの半分ずつとします。
アンカー設計間隔
Sa2=L2/2+L3/2 |
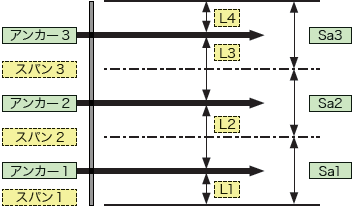 |
| ■図6 アンカー設計間隔と腹起し設計間隔 |
|
|
| 控え杭タイロッド式土留めでタイロッド間隔と控え杭間隔が異なるケースへの対応 |
前述のアンカー支保工の軸力分担幅と腹起し設計スパンの扱いと同様、Ver.8までは、控え杭タイロッド式土留めにおいて、タイロッド間隔と控え杭間隔は等しいものとして設計を行っておりましたが、本バージョンにて異なる場合に対応しました。具体的には、タイロッド間隔の1/2で控え杭を配置するなどといった検討が可能になりました。これに伴って、腹起し材の設計も土留め壁側と控え杭側の両方を検討するように改善しました。図面対応も行っております(図7、8)。
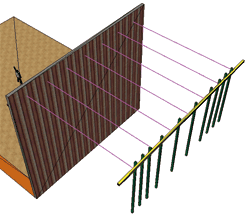 |
|
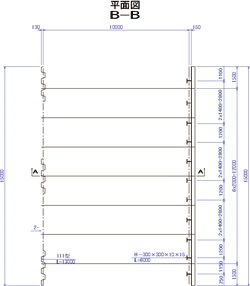 |
| ■図7 控え杭タイロッド式土留め3D描画 |
|
■図8 控え杭間隔を任意に設定した図面例 |
|
これまでにご紹介した機能以外に、
- 鉄道標準のヒービング照査に対応
- 親杭横矢板で、土留め板が軽量鋼矢板の場合にせん断照査を行えるように対応
- 親杭横矢板の土留め板の設計スパンに親杭間隔以外を設定できるように対応
- 中間杭の設計反力を実際にはありえない組合せ(全検討ケースのMax)ではなく、最終掘削時の反力を使用できるように改善
など、多くのご要望にも対応しております。
本製品はおかげさまで多くのユーザのみなさまにご愛用いただいており、ご要望も数多く頂戴しております。
今回対応できなかったご要望等に関しましても引き続き対応に向けて検討を進めて参りたいと考えております。 |
|







>> 製品総合カタログ

>> プレミアム会員サービス
>> ファイナンシャルサポート
|








